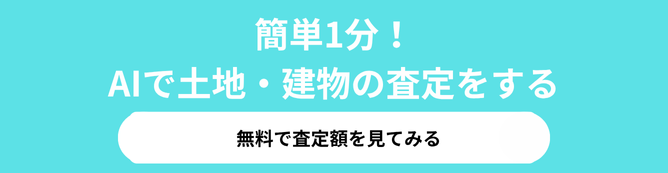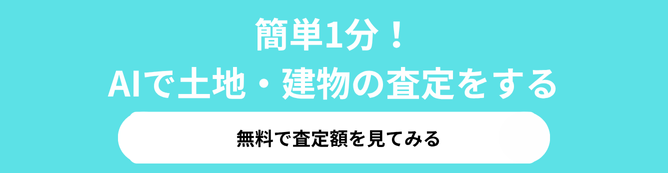こんにちは!大阪の東住吉区、平野区、東大阪市を中心に、皆様の不動産のお悩みに寄り添うNextOneです。
ご両親が遺してくれた大切なご実家を、兄弟姉妹で相続された、という方も多いのではないでしょうか。思い出の詰まった家を前に、感謝の気持ちと共に、「さて、この家をどうしようか?」という現実的な問題に直面しますよね。
特に、相続人が複数いる場合、法律上、その不動産は兄弟姉妹全員の「共有名義」という状態になります。これは、相続人全員で不動産を共同で所有している、という意味です。一見すると、公平で良い方法のように思えるかもしれません。
しかし、実はこの「共有名義」、将来的に思わぬトラブルの火種になることがあるのです。
今回の記事では、この共有名義のまま不動産を所有し続けることのリスクと、兄弟姉妹みんなが納得できる「円満な売却」を実現するための具体的なステップについて、詳しく解説していきます。
そもそも「共有名義」とは?知っておくべき大原則
共有名義とは、一つの不動産を複数人で所有している状態のことです。そして、それぞれの所有者が持つ権利の割合を「持分(もちぶん)」と言います。例えば、ご両親の家を兄弟3人で相続した場合、特別な取り決めがなければ、それぞれの持分は3分の1ずつとなります。
ここで絶対に知っておかなければならない大原則があります。それは、共有名義の不動産に関する重要な決定は、「共有者全員の同意」がなければ、一切進めることができない、ということです。
例えば、家を売りたい、誰かに貸したい、大規模なリフォームをしたい、といった行為は、たとえ持分が一番多い人でも、一人では決して決めることができません。兄弟3人のうち、一人でも反対すれば、その計画はストップしてしまうのです。
共有名義のまま放置する3つの大きなリスク
この「全員の同意が必要」という原則が、様々なリスクを生み出します。
リスク1:塩漬け状態になってしまう
例えば、兄弟のうち、長男は「売りたい」、次男は「誰かに貸したい」、長女は「思い出の家だから、そのままにしておきたい」と考えが分かれたとします。この場合、全員の意見が一致しないため、売ることも、貸すこともできず、結果として誰も使わないまま放置される「塩漬け」状態になってしまいます。家は人が住まないと、驚くほどのスピードで傷んでいきます。
リスク2:次の相続で、さらに複雑化する
これが最も見過ごされがちで、最も厄介なリスクです。
もし、兄弟3人のうち、長男が亡くなったとします。すると、長男が持っていた3分の1の権利は、長男の配偶者や子供たちへと相続されます。もし長男に妻と子供2人がいれば、権利を持つ人は「次男、長女、長男の妻、長男の子供A、長男の子供B」の5人に増えてしまいます。
世代が進むごとに、関係性の薄い親戚がどんどん増えていき、話し合いをまとめるのは絶望的に難しくなっていくのです。
リスク3:固定資産税の支払い義務は全員にある
誰も住んでいなくても、不動産を所有している限り、毎年固定資産税がかかります。納税通知書は代表者一人の元に届きますが、法律上は共有者全員に支払いの義務(連帯責任)があります。代表者が立て替えて後から精算する際に、「私は住んでいないのに、なぜ払うの?」といった金銭トラブルに発展するケースも少なくありません。
円満に売却するための3つのステップ
では、こうしたリスクを避け、全員が納得して売却を進めるには、どうすればいいのでしょうか。
Step1:全員で話し合い、売却の意思を固める
何よりもまず、共有者全員で集まるか、連絡を取り合い、不動産をどうしたいかについて話し合うことが大切です。その際、先ほど説明した「共有名義のままにしておくリスク」を全員で共有することが重要です。感情的な意見だけでなく、「将来、子供たちの代に迷惑をかけないために」という視点を持つと、全員が「売却して、現金で公平に分けるのが一番良い方法だ」という結論に至りやすくなります。
Step2:代表者を決める
全員の意思が固まったら、不動産会社との連絡窓口や、手続きの中心となる「代表者」を一人決めましょう。代表者は、査定の依頼をしたり、他の共有者に進捗状況を報告したりする役割を担います。窓口を一本化することで、情報が錯綜せず、スムーズに話を進めることができます。
Step3:全員が協力して契約手続きを進める
いよいよ売却が決まり、売買契約を結ぶ段階になったら、共有者全員の協力が必要です。契約書には、共有者全員が署名し、実印(市区町村に登録した印鑑)を押さなければなりません。また、その際に印鑑証明書などの公的な書類も必要になります。遠方に住んでいる方がいる場合は、事前に必要書類や手続きの流れを伝えておき、スムーズに準備できるよう協力し合うことが大切です。
よくあるトラブルと、専門家ができること
そうは言っても、親族間の話し合いはなかなか難しいものです。そんなときこそ、私たち不動産のプロを頼ってください。
・「売却価格で意見が合わない」
→ 私たちが客観的なデータに基づいた査定価格をご提示することで、公平な議論の土台を作ることができます。
・「特定の兄弟と連絡が取りづらい」
→ 中立的な第三者として間に入ることで、感情的な対立を避け、冷静に売却のメリットや手続きについてご説明し、説得のお手伝いをすることも可能です。
・「売却代金の分配が不安」
→ 売却代金は、司法書士という国家資格者が手続きを行い、登記簿に記載された持分割合に応じて、それぞれの口座に正確に振り込まれます。お金の分配でトラブルが起きる心配はありませんので、ご安心ください。
まとめ:円満な解決への近道は、専門家への相談です
兄弟姉妹で相続した共有名義の不動産は、放置すると将来のトラブルの元になりかねません。最も公平で円満な解決方法は、売却して現金化し、それぞれの持分に応じて分配することです。
そして、その話し合いや複雑な手続きを円滑に進めるためには、相続案件に詳しい不動産会社をパートナーに選ぶことが何よりも重要です。
私たちNextOneは、これまでにも多くの共有名義不動産の売却をお手伝いしてきました。どうやって話し合いを進めたらいいか分からない、という最初の段階から、どうぞお気軽にご相談ください。
あなたと、あなたのご兄弟姉e姉妹にとって、最善の解決策を一緒に見つけさせていただきます。