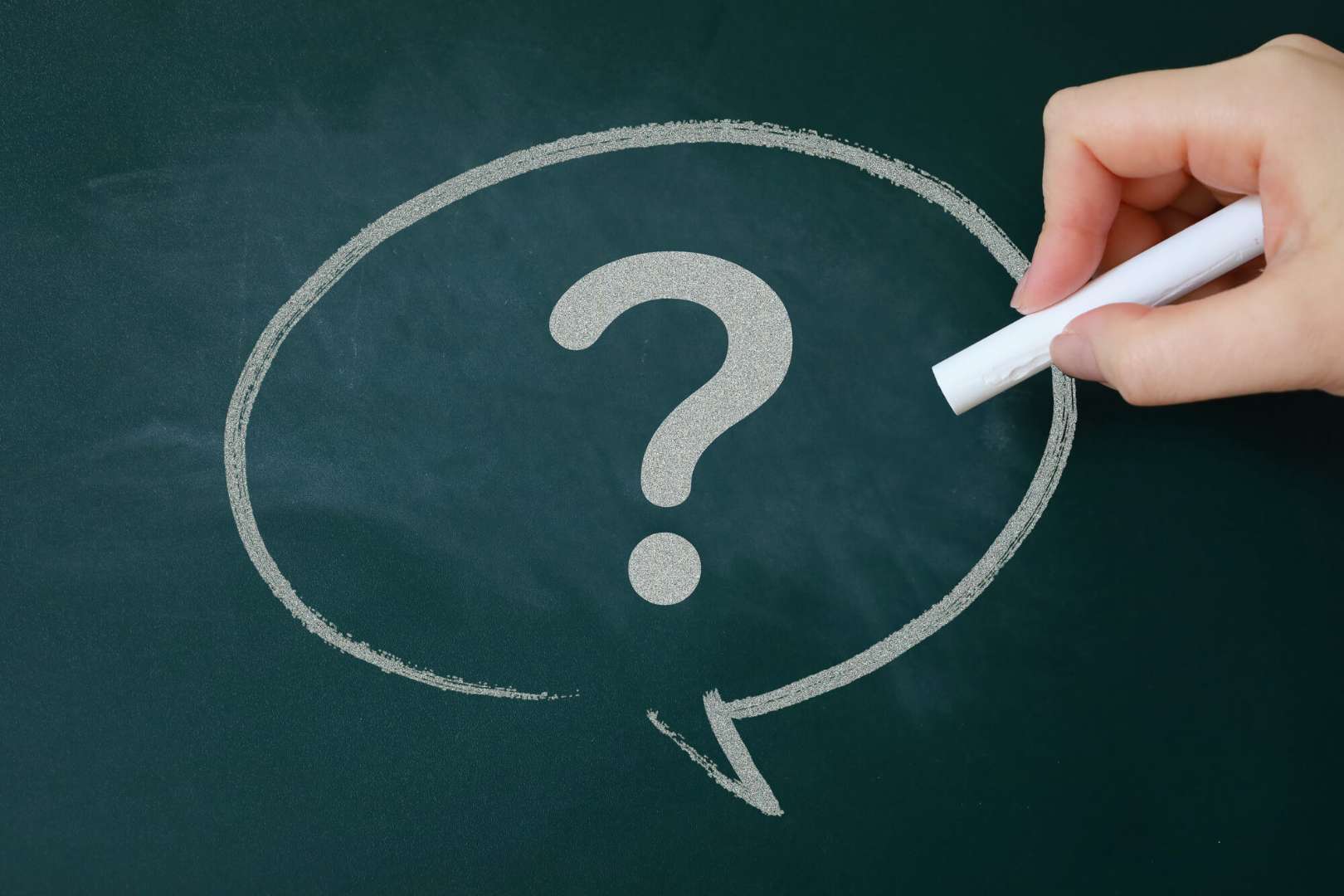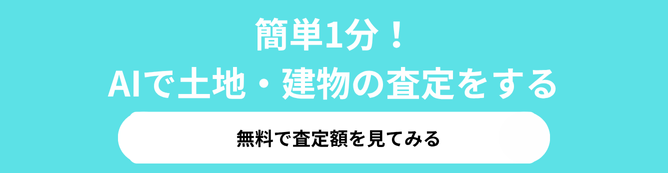築年数が経った家を売ろうとしたとき、多くの人が「こんな古い家じゃ買い手がつかないのでは…」という不安を感じるのではないでしょうか。たしかに新築や築浅の物件に比べると、古い家は買い手の目に留まりにくいことがあります。しかし、古いからといって「売れない」と決めつける必要はありません。
実際には、古い家でも需要のあるケースは存在します。立地が良ければ、建物よりも土地に価値を感じて購入する人もいますし、「リノベーション前提」で中古物件を探している人もいます。空き家活用や投資用として検討する層も少なくありません。
大切なのは、「自分の家はどういう売り方が適しているか」を見極めることです。現況のまま売るべきか、最低限の補修をすべきか、いっそ解体して更地として売るか——選択肢は複数あります。それぞれの可能性を把握した上で、現実的な戦略を立てることが、納得のいく売却への第一歩になります。
見た目・安全性・立地——買主の目線を先回りする
築年数の経った家を買おうとする人たちが、どこを見ているのか。これは売主が見落としやすい視点ですが、実は売却の成否を左右する重要な要素です。買主が重視するポイントは、主に「外観の印象」「構造の安全性」「立地環境」の3つに分けられます。
まず、外観や室内の状態は第一印象に大きく影響します。壁のひび割れや雨染み、雑然とした室内などは、築年数以上に「古さ」を強調してしまう要素です。たとえ構造に問題がなくても、こうした視覚的な印象だけで敬遠されてしまうこともあります。最低限の清掃や補修で印象が改善するのであれば、先に対処しておくのが得策です。
次に、安全性に関わる部分も見逃せません。耐震性やシロアリの有無、雨漏りや基礎のひび割れなど、建物の構造的な不安がある場合は、事前に「インスペクション(建物状況調査)」を実施しておくと、買主の不安を取り除く材料になります。これにより、売却後のトラブルも防ぎやすくなります。
そして、最も大きな要素の一つが「立地」です。駅からの距離や周辺環境、学校やスーパーとの位置関係などは、築年数に関係なく評価されるポイントです。特に古い家の場合、「家そのものの価値」よりも「土地のポテンシャル」に目を向ける買主が多くなります。
こうした買主目線を意識することで、売主としてできる工夫や準備が明確になります。自分の家のどこが評価されやすいのか、逆にどこに懸念を持たれそうかを冷静に見極めていくことが、価値を正しく伝える第一歩です。
「そのまま」「直して売る」「更地にする」最適な選択肢とは
築年数の経った家を売る場合、売主が最初に悩むのが「家を直すべきかどうか」という判断です。そのままの状態で売るのか、部分的にリフォームしてから売るのか、あるいは解体して更地として売るのか——それぞれにメリットとデメリットがあり、どれが正解とは一概に言えません。
まず「そのまま売る」場合、コストをかけずに売却できる点は大きなメリットです。買主が自由にリノベーションできることを前提にしていれば、現況のままでも十分魅力になります。ただし、外観や内部の状態によっては、買主の検討対象にすら入らない可能性もあります。
一方で「一部リフォームしてから売る」選択は、見た目の印象を大きく改善できます。たとえば、外壁の塗装や水回りの簡単な修繕などは、比較的少ない費用で売却価格や成約スピードに好影響をもたらす場合があります。ただし、リフォームにかけた費用がそのまま売値に上乗せできるとは限らず、費用対効果の見極めが難しい点には注意が必要です。
「更地にする」選択肢は、建物に価値がつかないと判断した場合に有効です。土地として売り出すことで、戸建て用地や収益物件向けとして需要が見込めるケースもあります。ただし、解体費用が数十万円〜百万円近くかかる場合もあるため、事前の見積もりと資金計画が不可欠です。
いずれの選択も、家の状態やエリアの需要、想定する買主層によって最適解が変わります。不動産会社と相談しながら、過去の事例や市場の動きもふまえて判断することが、後悔のない選択につながります。
古さが逆に「価値」になった売却事例とは?
築年数の古さは、一見すると売却の妨げに思えるかもしれません。けれども実際には、「古さ」が逆に強みとして働くケースも少なくありません。たとえば、古民家や昭和レトロな住宅を好んで購入する層は一定数存在します。内装や間取りの雰囲気に魅力を感じ、自分好みに手を加えながら住みたいというニーズです。
また、土地の需要が高いエリアでは、建物の古さは大きな障害にはなりません。「建物は使わずに、建て替え前提で購入する」という買主にとっては、家そのものよりも「立地」や「面積」「形状」のほうが重視されます。都市近郊や駅からのアクセスが良い地域であれば、築40年を超える物件でもすぐに買い手が見つかるケースがあります。
さらに、最近では空き家活用や投資物件としての需要も増えています。個人の買主だけでなく、不動産投資会社や建築事務所、事業用地を探す法人などが「リフォーム前提」「解体前提」で購入するケースもあり、「古い=価値がない」とは言い切れないのです。
こうした事例に共通しているのは、適切な「買主層の想定」と「売却戦略の設計」がなされていたことです。売主が一人で判断するのではなく、地域の特性や買い手の傾向を知る不動産会社のアドバイスを受けながら、現実的な落としどころを見つけた結果といえるでしょう。
ネクスト・ワンのように、地元の事情に精通し、多様な相談を受けてきた不動産会社であれば、一般的な流通ルートだけでなく、ニッチな需要にも柔軟に対応できます。売れないと思っていた家に、思いがけない価値が見いだされることもあるのです。
→ https://www.nextone2021.com/nexthome
築年数が影響する「法的・税務リスク」とその対処法
古い家を売る際に注意したいのが、見た目や価格だけではありません。契約や法律、税金の面でも、築年数が与える影響は無視できない要素です。特に重要なのが、「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」や「建物状況の説明義務」に関する部分です。
築年数が経った物件では、雨漏り・基礎のひび割れ・シロアリ被害など、売主が気づいていない不具合が残っている可能性があります。これを放置したまま売却し、引き渡し後に問題が発覚すると、損害賠償や契約解除といったトラブルに発展することもあります。こうしたリスクを避けるためには、売主側から建物の状態を積極的に開示することが不可欠です。
その手段のひとつが「インスペクション(建物状況調査)」の活用です。専門の第三者が住宅の状態を調査し、その結果を買主に示すことで、信頼性が高まるだけでなく、後々の責任範囲も明確になります。とくに築年数の古い物件では、この調査を通じて売却条件の交渉がスムーズになるケースが増えています。
また、税務上の注意点としては「譲渡所得税」があります。古い家であっても、購入当時と比べて価格が上がっていれば、利益に対して税金がかかります。ただし、「所有期間が10年以上」「マイホームとして使用」などの条件を満たす場合は、3,000万円の特別控除が受けられる制度もあるため、早めに確認しておくとよいでしょう。
その他にも、相続した空き家を売る場合には、「被相続人居住用財産の特例」など、築年数や使用状況に応じて適用される税制も存在します。これらの制度は年によって変更される可能性もあるため、税理士や不動産会社と連携しながら進めることが、安心して売却を進める鍵になります。
売却の可能性を広げるには「正確な評価」と「最適な提案」が鍵
築年数の古い家でも、「売れない」と決めつける必要はありません。大切なのは、家の状態や地域の需要を正しく評価し、それに合った方法で売却戦略を立てることです。表面的な印象だけで判断せず、建物の安全性や土地の魅力、買主層のニーズを丁寧に見つめ直すことで、売却の可能性は大きく広がります。
自分だけで判断するのが難しいと感じたら、まずは経験豊富な不動産会社に相談することをおすすめします。地域密着で数多くの築古物件を取り扱ってきた実績があれば、思いもよらない提案や販売ルートが見つかることもあります。
気になる方は、無料相談から始めてみてはいかがでしょうか。